 みんなの御朱印
みんなの御朱印
 自分の御朱印
自分の御朱印
まだ御朱印が登録されていません
 みんなの参拝記録
みんなの参拝記録

0
102

0
122
 自分の参拝記録
自分の参拝記録
まだ参拝記録が登録されていません
 みんなの動画
みんなの動画
 自分の動画
自分の動画
まだ動画が登録されていません
 基本情報
基本情報
※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。
| 住所 |
埼玉県桶川市川田谷215 |
五畿八道
令制国 |
東海道 武蔵 |
| アクセス |
JR高崎線桶川 徒歩47分 |
| 御朱印授与時間 |
|
| 電話番号 |
048-725-2069 八枝神社 |
| FAX番号 |
|
| 公式サイトURL |
|
| 御祭神 |
素戔嗚尊 |
| 創建・建立 |
|
| 旧社格 |
旧村社 |
| 由来 |
境内掲示板
氷川神社 桶川市川田谷ニー五
祭神・・・素戔嗚尊
当社が鎮まる樋詰の地は、荒川左岸の低地に位置し、古くから度重なる水害を被ってきた。樋詰は川田谷村の枝郷で、慶安ニ-三年(一六四九- 五〇)の『田園簿』では本村に含まれており、元禄十五年(一七〇)の 『元禄郷帳』では川田谷村枝郷として樋詰村一〇二石余と記される。また、ロ碑によれば、樋詰の開発当初の村人は長島一家だけであったという。
その創建は川田谷村から分村する過程で祀られたことが推測され、長島一家とのかかわりも考えられる。化政期(一八〇四 - 三〇)の『風土記稿』川田谷村枝郷樋詰村の項には「氷川社 村の鎮守なり、川田谷村西光寺の持」とあり、当時の家数は三三戸とある。
参道入口の鳥居に掲げる「氷川大明神」の額には、裏に「元文四未(一七三九)天十一月吉日 武州足立郡石戸領樋誌村氏子中」と刻まれており、 当社の最も古い史料となっている。また、本殿に安置する金幣には「奉献 心願成就 明和六己年丑(一七六九)二月吉日」「願主伊勢屋丑兵衛」と記されている。
明治六年に当社は村社となり、昭和四十二年には社務所兼集会所を攻築した。また、往時の別当西光寺は既に廃寺となっており、その跡には墓地が残る。
祭神の素戔嗚尊は八岐大蛇を退治したことで有名であるが、八岐大蛇とは一説には大雨で暴れた川を表し、その水害を鎮めるための守り神として祀られたと考えられる。
祭礼は正月の歳旦祭、二月の恵比須講(祈年祭)、十月のお日待ち、 十一月の恵比須講(新嘗祭)の年四回である。
社殿東隣に「稲荷社」を祀り、境内南東には「庚申塔(青面金剛)」が 祀られている。
宮司連絡先:〇四八(七二五)二〇六九
|
| 神社・お寺情報 |
境内掲示板
桶川市指定文化財 樋詰の道しるべ
種別: 民俗文化財 (有形民俗) 平成8年5月29日指定
この道しるべは、高さ40cmほどの小さな道しるべです。明和8年(1771)に建てられ、正面には「あきは道」「大宮道」とあります。「あきは」は火災除け、盗難除けの神様として信仰を集めた指扇村(現さいたま市)の秋葉神社で、「大宮」はさいたま市の武蔵一宮氷川神社です。正面向かって右側面には「かうのす道」、左側面には「太郎ヱ門舟渡」と刻まれています。「太郎ヱ門舟渡」は、現在の県道12号川越栗橋線の太郎右衛門橋付近にあった荒川の渡し場のことです。
樋詰氷川神社の前の道は、古くからの主要道路であったと考えられ、沿道には城館跡や寺社などが多く残されています。 江戸時代には中山道の脇道として、また、荒川の舟運や渡河のための主要交通路として、多くの人の往来があったと思われます。 この道しるべも、 通行する人々の案内役として重要な役割を果たしていたことがうかがえます。
平成27年3月 桶川市教育委員会 |
| 例祭日 |
|
| 神紋・寺紋 |
 未登録
未登録
|
| 更新情報 |
【
最終
更新者】shim
【
最終
更新日時】2026/01/08 19:57:01
|
※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は
こちらよりお気軽にご相談ください。

 近くの神社・お寺
近くの神社・お寺
 近くのお城
近くのお城
神社・お寺検索
※は必須です
※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は
こちら。
 みんなの御朱印
みんなの御朱印 自分の御朱印
自分の御朱印 みんなの参拝記録
みんなの参拝記録 自分の参拝記録
自分の参拝記録 みんなの動画
みんなの動画 自分の動画
自分の動画 基本情報
基本情報










 未登録
未登録

 近くの神社・お寺
近くの神社・お寺


 神社日別アクセスランキング
神社日別アクセスランキング
 川中島古戦場八幡神社
川中島古戦場八幡神社

 堀之内愛宕神社
堀之内愛宕神社
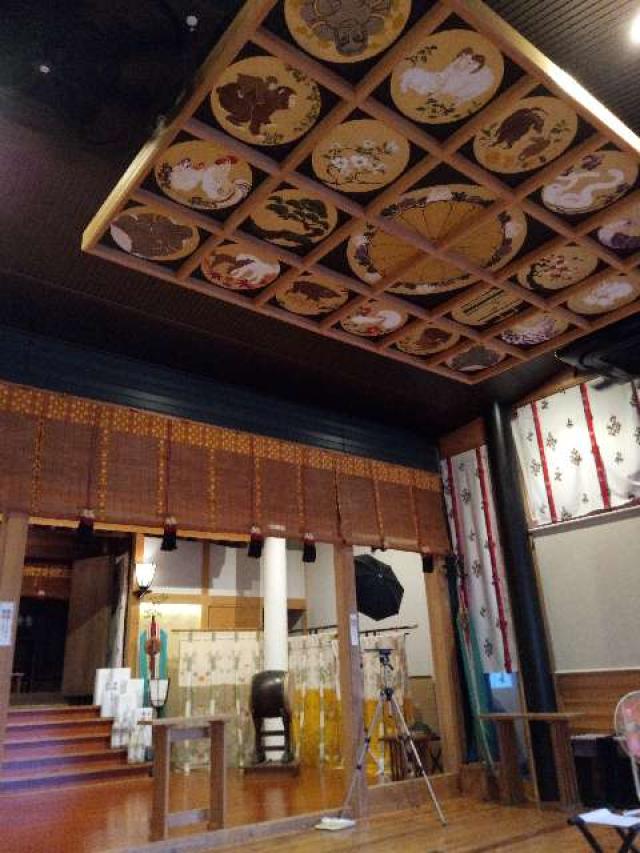
 菊名神社
菊名神社









 新着・更新寺社情報
新着・更新寺社情報





 神社・お寺ニュース
神社・お寺ニュース



