 みんなの御朱印
みんなの御朱印
 自分の御朱印
自分の御朱印
まだ御朱印が登録されていません
 みんなの参拝記録
みんなの参拝記録
 自分の参拝記録
自分の参拝記録
まだ参拝記録が登録されていません
 みんなの動画
みんなの動画
 自分の動画
自分の動画
まだ動画が登録されていません
 基本情報
基本情報
※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。
| 住所 |
埼玉県熊谷市久下1834 |
五畿八道
令制国 |
東海道 武蔵 |
| アクセス |
秩父本線熊谷 徒歩20分 |
| 御朱印授与時間 |
|
| 電話番号 |
0485220366 |
| FAX番号 |
0485263811 |
| 公式サイトURL |
|
| 御本尊 |
|
| 宗派 |
曹洞宗 |
| 創建・建立 |
|
| 由来 |
新編武藏風土記稿
大里郡久下村
東竹院 禪宗曹洞派下總國結城孝顯寺末梅籠山久松寺ト號ス古ハ天台宗ナリシト云本尊釋迦寬永十九年三十石ノ御朱印ヲ附セラル開基ハ久下次郞重光建久七年七月三日卒ス東竹院久遠順昌居士ト號ス又久下權守直光元久元年甲子四月二十九日卒ス長和院天了慧運居士コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト東鑑ニ其コトハ見エス直光ハ熊谷直實ノ姨母ノ夫ナリト載ス尙村ノ名條見合スヘシ開祖ハ月擔承水法師安貞元年八月七日示寂中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郞憲賢ニテ永祿十一年七月二日卒ス此時ノ僧ヲ的翁文中ト云天正十三年八月十七日寂セリ
寺寶袈裟一領 蜀江ノ錦ニテ雲手ノ模樣アリ上杉家ノ寄附ト云 成田分限帳一册 山門 衆寮 鐘樓 鐘ハ嘉祿ニ鑄シ物ニテ賀美郡阿保村眞光寺ノ鐘ナリ戰國ノ世ニ行軍ノ人奪去リシニ後村內ウナギ淵ヨリ掘出セシト此鐘ニ鐵砲ノ玉入テアリトテ其銘爰ニ載ス奉鑄武州賀美郡阿部村眞光寺鐘右志者爲信心大檀那小野氏沙彌阿彌陀佛現□安穩後世□善處兼法界衆生平等利益也嘉祿三年大才丁亥五月日 白山社 久下墓 五輪ナリ久下氏ト云ヘト詳ナラス恐ラクハ次郞重光カ墓ナルヘシ 上杉墓 又五輪ナリコレモ名ヲ傳ヘサレト三郞憲賢ノ墓ニヤ
境内碑
東竹院秀道和尚孝顯現住百英昭和三年七月十五日中興號授
梅籠山東竹院ハ深谷城主上杉憲賢公中興開基ニシテ我ガ天
女山孝顯寺第五世的翁文中禅師ヲ開山ニ請シ臺家ヲ改メテ
禅苑ト為シ伽藍堂塔荘厳ヲ極メタレドモ嘉永年間祝融ノ災
ニ罹リ復旧ノ後安政ノ水難流失ノ厄ニ遭ヒタルガ現住岸秀
道和尚再興ノ大願ヲ発シ門葉檀信ト相謀リ本堂再建庫院ノ
改築ヲ遂ゲ更ニ衣資ヲ割キテ境内ニ達磨大使ノ大石像ヲ安
置シ避邇歸祟ノ霊場ヲ完成セリ山僧主功續ノ偉ナルヲ認メ
特ニ中興ノ称号ヲ授ケテ嘉尚ノ意ヲ表シ後代之ヲ継グ者ヲ
シテ其由ル所アルコトヲ知ラシム
昭和三年七月十五日 本寺天女山孝顯寺現住百英識
境内碑
本尊釈迦牟尼如来を安置し、曹洞宗梅龍山東竹院と称す。開基は豪族久下次郎重光公にして、建久二年比叡山天台の高僧 月檐承水法印を請し開山とす。久下氏は私市党の一族にして、私市家盛の弟為家 始めて久下村に居住し久下太郎と称す。直光公及びその子重光公は、源頼朝挙兵石橋山合戦以来それに從い、特に土肥の杉山にては第一番に頼朝の陣に馳せ参じ、一の谷の戦に武功あり、平氏が壇の浦に退くを追って遠く九州に赴き、久下氏多年の軍功を賞して丸一の家門と領地を賜る。これ当寺の定紋の所以なり。爾来三百有余年過ぎ堂宇廃領せるを、深谷城主上杉三郎憲賢公中興開基し、下総国結城 孝顯寺五世 的翁文中和尚を請して開山となし、改めて禅宗曹洞宗となる。伽藍善美を尽くし寺格随意会地となり、幕府徳川氏より代々寺領三十石の朱印を賜る。檀信徒五百余戸の福地として隆盛を極む。しかるに、嘉永七年火災のため伽藍全焼し更に安政六年荒川大洪水のため全潰す。後年大正年間に秀道和尚、門葉寺院並びに檀信と謀り、七堂伽藍の大改築を果す。本寺 孝顕寺百英和尚その功の偉大なると認め、中興の称号を贈る。
境内安置の天然石像達磨大師は、高さ一丈余重さ四千貫にて、遠く寛文年間忍の城主阿部豊後守、深く大師禅宗始祖を尊崇し、城中へ招致せんとなし、秩父の山中より筏上に積載運搬中、当山の領地にて墜落せしものにて、以来二百余年間河底に面壁の侭埋没し、空しくその名を伝うるのみとなる。秀道和尚深くこれを惜み、同志相謀り官許を得て、大正十四年春 遂にこれを境内に安置の霊石となす。
爾来二十星霜 昭和二十年八月十四日夜半米軍の空襲を受け、終戦前夜にしてさしもの大伽藍灰塵と化したり。国敗れて窮乏に落ち、現住秀正和尚燋土に立ちて大願を発し、門葉檀信と一丸となりて漸次堂閣を新築し、伽藍完備旧態を超すに至る。之を嘉尚し以て撰する者なり。
平成三年十月 開創八百年祭吉祥日
天女山孝顕寺三十八世 彬道恵文 撰文 |
| 神社・お寺情報 |
境内碑
達磨石
重さ約十五トン
高さ約三メートル
今から千六百年ほど昔南インドに生まれ その後百歳を超えてから今の中国に渡り 真の仏法を伝え禅宗の祖となった菩提達磨大和尚は 人間としての真の姿に目覚めた人 また大変に辛抱強い立派なお坊様として広く知られています
この達産石は 今から三百五十年ほど前の寛文年間に 忍城主阿部豊後守忠秋の命により 秩父山中から荒川を筏に載せて運搬途中久下で河中に転落してしまいました その後大正十四年に東竹院前の河原で発見されるまで 不思議にも二百六十年の間に転落した所から二キロメートルも荒川を遡ったと言われています その年 寺院二十六世 檀信徒 青年団等たくさんの人々の発意と努力によってここに安置されました
中央の丸い穴は 自然が非常に長い年月をかけて形成したもので 横から眺めると本当に達磨さんが坐禅をしている様に見えます
私たちが人間としての自覚と真の幸福とを願うとき 達磨大師の素晴しい忍耐力と教えに正しく学ぶ心を持ちたいと思います
平成十六年
梅籠山久松寺東竹院二十九世天渓世一識
白汀野口林造書
㈲野口石材店
畊石野口孝刻 |
| 例祭日 |
|
| 神紋・寺紋 |
 未登録
未登録
|
| 更新情報 |
【
最終
更新者】thonglor17
【
最終
更新日時】2023/05/03 17:32:16
|
※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は
こちらよりお気軽にご相談ください。

 近くの神社・お寺
近くの神社・お寺
 近くのお城
近くのお城
神社・お寺検索
※は必須です
※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は
こちら。
 みんなの御朱印
みんなの御朱印 自分の御朱印
自分の御朱印 みんなの参拝記録
みんなの参拝記録 自分の参拝記録
自分の参拝記録 みんなの動画
みんなの動画 自分の動画
自分の動画 基本情報
基本情報







 未登録
未登録

 近くの神社・お寺
近くの神社・お寺


 神社日別アクセスランキング
神社日別アクセスランキング
 平田神社
平田神社

 南水元富士神社(飯塚富士神社)
南水元富士神社(飯塚富士神社)

 氣比神宮
氣比神宮









 新着・更新寺社情報
新着・更新寺社情報

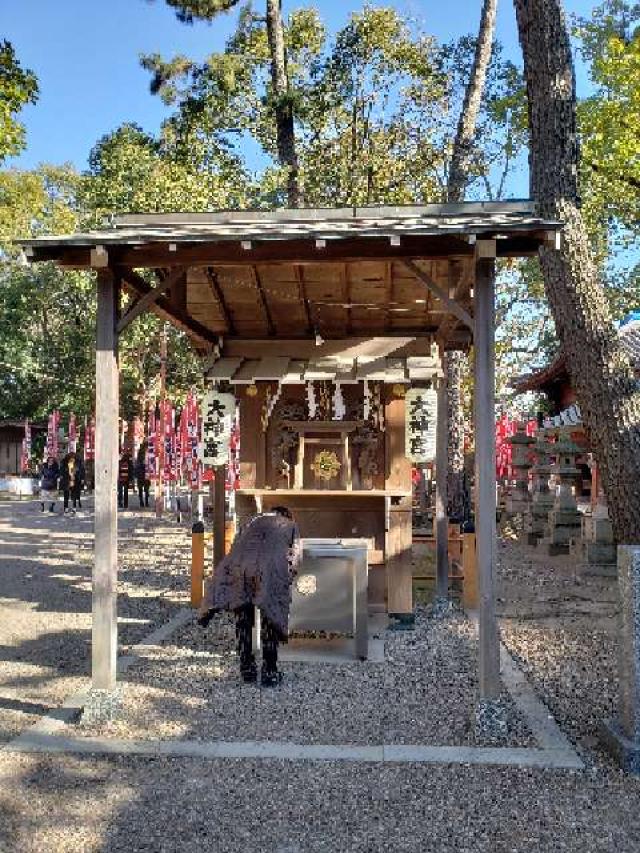





 神社・お寺ニュース
神社・お寺ニュース



